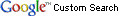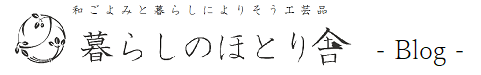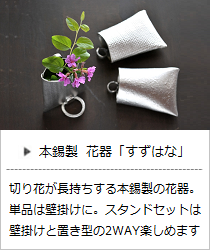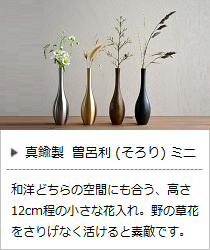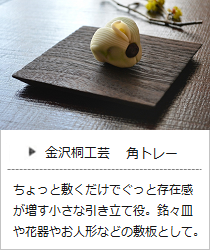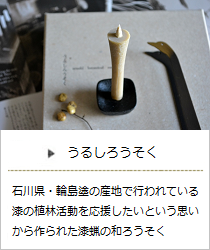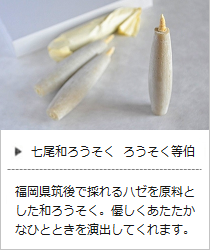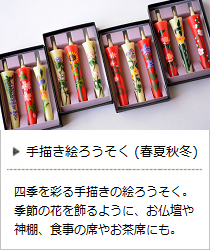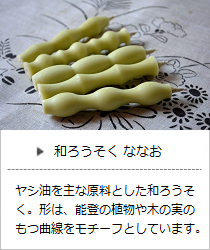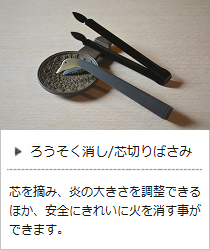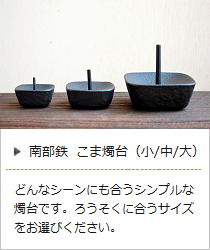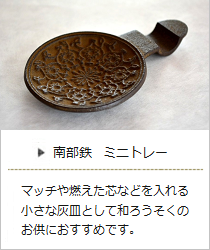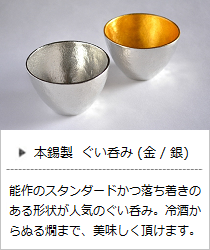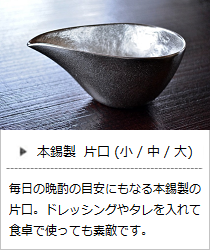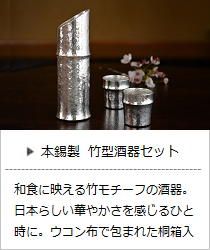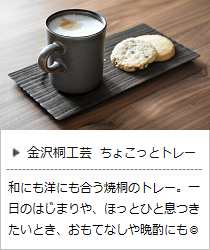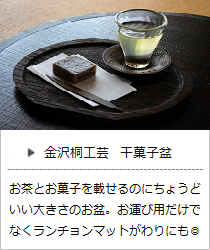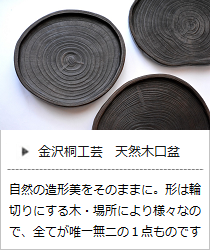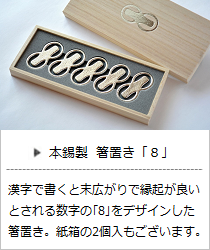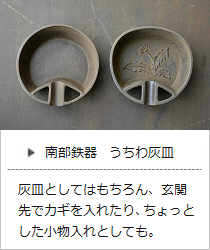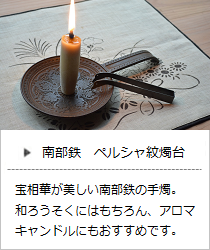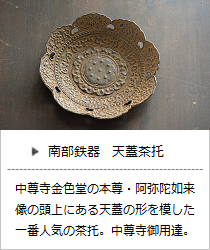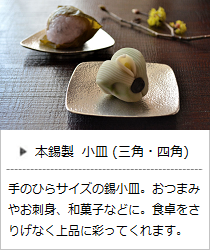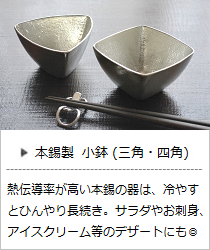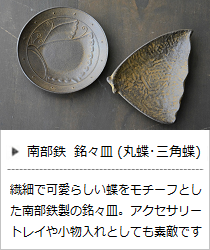夏越の祓(なごしのはらえ)
1年のちょうど折り返しとなる、6月の晦日。
この日には、各地の神社で「夏越の祓」が行われます。
夏越の祓とは、半年分の罪穢れを祓い、残り半年の無病息災を願う神事です。
大晦日が新年を迎えるための大切な日であったのと同じように、6月の晦日もまた、物忌みの日、祓いの日と考えられてきました。
昔、宮廷では、12月晦日と6月晦日の年2回、「大祓い」の神事が行われていましたが、12月の方を「年越し」と呼ぶのに対し、6月の方は「夏越し」と呼んでいました。
6月も末に近づくと、全国の多くの神社の境内には、茅 (ちがや) で作った大きな「茅の輪 (ちのわ)」が飾られます。
![茅の輪[貴船神社・京都府京都市左京区]|暮らしのほとり舎](../_src/33379940/chinowa_kifunejinja_kyoto.jpg?v=1767273206998)
この輪をくぐると、知らず知らずのうちに溜まっていた半年分の厄と穢れが祓われ、寿命が延びると言われています。
「水無月の夏越の祓をする人は、千歳の命延ぶというなり」と唱えながら、左回り・右回り・左回りの順に、8の字を描くように3度くぐり抜けます。
![茅の輪くぐり[穂高神社・長野県安曇野市]|暮らしのほとり舎](../_src/33380656/chinowakuguri_hotakajinja_azumino.jpg?v=1767273206998)
茅は、原野や河原に群生するイネ科の多年草で、茎と葉は屋根を葺くのに使われます。
戸部民夫 (著)『神秘の道具 日本編』によると、茅の輪は魔除けや疫病除けの呪力を秘めており、その力は、神社の境内で皆がくぐる大きなものに限らず、小さな茅の輪を家の戸口に下げたり、腕や腰に付けてお守りとすることでも、厄除け、魔除けとして効果があるそうです。
そもそも茅そのものが古くから神を招きよせる標識であり、魔除けの機能があると考えられてきたそうです。
![茅の輪ミニ[貴船神社・京都府京都市左京区]|暮らしのほとり舎](../_src/33380653/chinowa-mini_kifunejinja_kyoto.jpg?v=1767273206998)
上画像のミニ茅の輪は、京都の貴船神社で購入したものです。
茅の輪くぐりをし、さらにミニ茅の輪を玄関に掛けておけば、夏の厄除けはばっちりです。
季節の楽しみいろいろ

「夏越の祓」の時季におすすめの商品

▲ Page Top
最近の投稿記事
2025.10.28
2025.09.14
2025.02.15
2025.02.07
2024.03.17
2024.01.24
【令和6年能登半島地震】売り上げの一部を被災メーカー2社へ寄付致します
2023.10.21
Archive